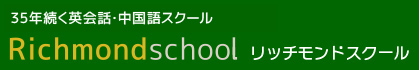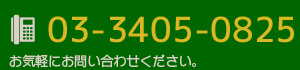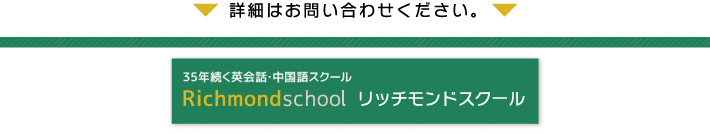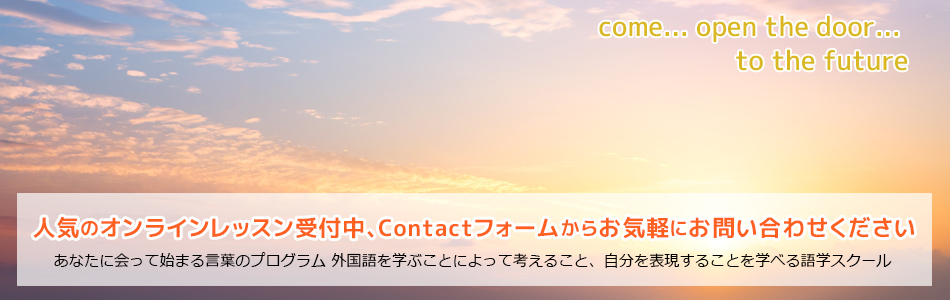
BLOG
ドイツには真理と正義が
2015/03/23
メルケル首相は、来日し脱原発を決意した理由について
「素晴らしい技術水準を持つ日本で事故が起き、
本当に予期できないリスクがあることが分かった」と語った。
ドイツは、福島の事件で原発を止めることを決心し、
事故を起こし世界中を混乱におとしめた日本が原発再稼働を決める。
奇妙ではないか?
日本ではその責任を取らないのか?
また、戦後処理に関して、
ドイツが欧州で和解を進められたのは
「ドイツが過去ときちんと向き合ったからだ。
隣国(フランス)の寛容さもあった」と述べた。
ドイツは、戦争責任を認め、過去の誤りと反省を諸外国に示したことにより
近隣諸国と平和を築けた。
ドイツ人にはあまり馴染みがないが、
メルケル首相の会見を聞く限り、
ドイツには真理と正義がある。
かつて医学、科学、音楽、文学どの分野においてもドイツは優れていた。
ゆえに、昔の日本の知識人はドイツ語を話した。
アメリカが世界の警察ではなくなった今、
メルケル首相は
欧州だけでなく世界を牽引して指導力を発揮している。
人間として女性として頼もしい。
ドイツ語もやらなければ・・・。
スイスの大使公邸を移築した翠州亭@千葉県
想像力の欠如
2015/03/11
近ごろ足りないことだらけ。
人を思いやる心。
13歳の中学生が殺され、
加害者の少年たちに被害者の恐怖や気持ちを想像できなかったこと。
今になって、とんでもないことをしたと、言っているとか。
目の不自由な人を、足蹴にして恐怖に陥れてたり、
お年寄りや弱者に対し、
邪魔者扱いするような態度をしたり、
彼らがどんな思いで、諦め我慢しているか想像できない人。
戦後70年、平和を維持し世界から称賛を浴びてきた日本が、
列強と並ぶような、勇ましい挨拶をしたら、
諸外国からどのように思われるか想像できないこと。
想像力の欠如は、
書物を読み、歴史を学び、先達に学び、知識を広めること等の不足。
上も下も欠如した人間だらけ。
中曽根元首相も
「ようするに歴史的思考っていうものがなくなった。
現実的な明日をどうするっていうのはあるが、
哲学を背景にした深い思索を持ったものがない。」
歴史を見返し、過去から学び、
哲学を持って、深い思索をし、
そこから未来を見据える。
“今、目の前にあるもの”しか見えていないから、
気が付いた時には、
とんでもないことをした、
とんでもない方向に行ってしまった、
となる。
道徳を教科にするなら、
歴史や哲学からの洞察力を学ぶようにして欲しい。
つつましく満開になった梅、可憐で綺麗。
感動でした
2015/03/06
リッチモンドスクールを始めて28年になる。
その間、本当に色々な出会いがあった。
中には思い出したくない想い出も沢山あるが・・・。
先日、ある生徒さんの紹介で、と言う方から電話があった。
その生徒さんは1年も在籍して居なかった方だったが、
ピラティスの先生で、英語はかなり上手で、チャーミングで、
ハキハキしたお嬢さんだという事を、はっきり覚えている。
10年以上も前の生徒さんなのに、
リッチモンドスクールを覚えていてくれて、
紹介して下さったこと。
感謝でいっぱいだ。
私が始めた頃は、
英会話スクールは少なく、ずいぶん遠方からも生徒さんが通って下さった。
今は、英会話スクールが必ず近所に何軒かあるため、
紹介も難しい。
私は、何かを買う場合、食事をする場合でも、
なるべく知っているところを利用する。
同じお金を落とすなら、
知っている人に落としたい。
自分でコツコツと仕事をしている身として、
わざわざ内を選んでくれたという感謝の気持ちは、計り知れない。
長くやってきて本当に良かったと思える瞬間。
あらゆる人に感謝したくなる。
紹介下さった生徒さんは、
来週からリッチモンドスクールの生徒さんになる。
あっという間に満開になったヒヤシンス
初心に帰って
2015/02/25
晴子先生が体調をくずして1か月の休養に入った。
代理の先生に代講して貰っている。
現在ベテランの先生が多いので、
最近リッチモンドスクールのメソッドを振り返ることがなかった。
代講の先生も決して下手ではないのだが、
20年以上も通っている生徒さんからすると不足らしい。
ベテランの生徒さん達は、
まさに違いが分かる生徒さんで、
先生のジャッジ、授業内容のジャッジ、教え方のジャッジが鋭い。
感想を伺うと、
悪くはないけど、、、普通の英会話スクールと同じ、、と、
厳しいフィードバックが返ってくる。
改めてリッチモンドスクールのTeaching Methods, Teaching Guidebook等を
見直してみた。
リッチモンドスクールでは、
習う→理解する→覚える→使える→自分のものになるまで、
しつこく授業をする。
勉強したことが、自然に口に出てくるまで、
何回も何回も繰り返し、自分のものとして習得した段階で次に進む。
従って、カリキュラム通りに進むなんてことはなく、
先生の教えたい授業ではなく、
生徒さんに合わせ(理解度、習得度、またバックグラウンド、趣向、趣味等)
頭と心にストンと落ちた納得のいく授業を行う。
語学習得は時間がかかるものだし、一旦諦めたらゼロになる。
一日一ミリ進めば良いのだ。
まさに継続は力なり。
怒りではなく、優しさに
2015/02/16
米国のパワー国連大使は、人質事件の犠牲になったフリージャーナリスト
後藤健二さんらの活動を紹介し、功績をたたえた
「ケンジは紛争を伝えることに人生を懸け、賞を受けた子ども向けの著書
『ダイヤモンドより平和がほしい』では、シエラレオネの元少年兵の物語を伝えた」
と述べた。
外国では、彼の功績をたたえる人々のニュースが多い。
一方日本では、ネット等で後藤さんに対して厳しい書き込みがある。
自己責任が90%近く、迷惑だ、の声が多い。
勝手に行った人を税金で助ける必要はない。
後藤さんを残酷なほど怒り、憎んでいるようだ。
また、本人の過去を暴き、家族や身の回りの人までも悪者に仕立て上げている。
匿名だけでなく、週刊誌までも書きたてている。
なぜ彼に、そんな意地悪を言えるのか?
その言葉の暴力は、残忍な殺人集団イスラム国と同列ではないか。
彼を、なぜそこまで感情的に憎む必要があるのか?
同じ日本人として悲しく、恥ずかしい。
2万回を超えた有名なツイート
「目を閉じて、じっと我慢。怒ったら、怒鳴ったら、終わり。
それは祈りに近い。憎むは人の業にあらず、裁きは神の領域。
そう教えてくれたのはアラブの兄弟たちだった」(22年9月7日)
以下は彼の出身校である法政大学学長の言葉
「いかなる理由があろうと、いかなる思想のもとであっても、また、
世界中のいかなる国家であろうとも、人の命を奪うことで己を利する行為は、
決して正当化されるものではありません。
暴力によって言論の自由の要である報道の道を閉ざすことも、
あってはならないことです。」
この後も、心に響く言葉が続く。
http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/socho/message02.html
春はそこまで
フランス語・イタリア語開講
2015/02/09
リッチモンドスクールでは、
最近、生徒さんからフランス語とイタリア語クラス開催の要望があり、
今年から実施している。
以前にも、生徒さんの要望に合わせ、
スペイン語やイタリア語クラスを実施したことがある。
我々スタッフが、英語しか話せないので、
イタリア語やフランス語を聞いていると、ワー、カッコイイ、と感嘆する。
先生方は、皆、英語と日本語を話すので、
コミュニケーションは問題ないのだが、
何だか肩身が狭い。
また、子供たちは、
フランス語でも中国語でも覚えも早く、発音も良く、
本当に羨ましい。
3歳からリッチモンドスクールで英語を学び、
現在小5年生のK子ちゃんは
英語のほかに、仏語と中国語を始めた。
賢いお嬢さんなので、楽しんで学んでいる。
K子ちゃんの将来、楽しみだ。
子供の頃から、数か国語を学び、
日常会話くらいは話せ、
少なくとも、聞けるようになれば、
世界中、何処に行ってもawayの状態に陥らない。
平常心で活躍できるだろう。
先日行った宮古島で、
伊良部島と宮古島を結ぶ開通ホヤホヤの伊良部大橋を通行
ジャーナリスト
2015/01/31
このブログを書いている間にも、変化があるかもしれないが
日本中、ひっくり返ったような騒ぎになっている。
「”自己責任“だから、同情できない」
「勝手に行ったのだから、関係ない」
「危険を承知で行った人に、我々の税金を使う必要はない」
そのような意見がかなり聞こえてくる。
海外では決して、そのような声は聞かれないとか。
日本人は冷たいという報道もかなりみられる。
紛争地帯や、戦争地帯を報道することは重要な事。
戦場ジャーナリストが、
危険だと言って放っておけば、
何も伝えられず、
酷いことが起こっても世界から見放され、人権が守られない。
ソマリアの様にあまりに危険だったため、
惨状を伝えるジャーナリストが逃げ、
虐殺など人道問題が続いていて、世界から見捨てられた。
危険を顧みず、我々に惨状が届けられることで、
他国の目が向けられ、人権が守られ、人道支援の輪が広がり、
世界平和への一歩となる。
中東では、中立とみられ好かれていた日本人が、
積極的平和主義とやらで、西欧側に巻き込まれてしまった。
今後、我々日本人の立場はどうなるのか?
グローバル社会で賢く生き抜く知恵を、
為政者は慎重に考慮して行動して欲しい。
明治神宮初詣
凛とした気分になる。
読売交響楽団
2015/01/26
読響の会員になって5年になる。
定期演奏会やマチネーシリーズがあるが、友人と二人で入っているのは
“サントリーホール名曲シリーズ”。
年に11回のコンサートを楽しめる。
以前、サントリーホールに隣接するIntercontinental Hotelで
開演前にシャンペン飲み放題付きディナーに行き、
第九の大合唱を聞きながら、良い気持ちでスヤスヤと。
それ以降は、始まる前の食事では決して飲まないことにしている。
また、休憩時間にワインをオシャレに傾けると、後半は睡魔との闘いになる。
昔、ロンドンで友人が用意してくれたバルコニー席でワインを飲みながら
オペラを鑑賞した時も、爆睡してしまい全く猫に小判であった。
そんな数々の失敗にもめげず
5年もクラッシック鑑賞を続けている。
今月は嬉しいことに
高校時代にリッチモンドスクールで英語を習っていた
マリンバ奏者の小森邦彦さんが客演した。
彼は現在、国際的に活躍していて世界で注目されている。
彼の奏でるマリンバ独特の音色のお蔭で、
昨日から胸につかえていた鉛がスーと解け、
心が軽やか、微笑みになった。
そして後半は、
下野竜也さんの渾身のタクトで、マーラー第5番。
トランペット、ホルン、数々の管楽器、打楽器、ハープ、
舞台いっぱいのオーケストラ。
溢れるほどのエネルギーを感じ、
元気溌剌になって帰途についた。
カラヤン広場
Je suis Charlie — I am Charlie
2015/01/19
フランスでの惨劇は
日本でもどんよりとした深い悲しみに包まれた。
表現の自由とテロへの脅威に屈しないというスローガンのもと、
ヨーロッパの首脳が腕を組んで悲痛な面持ちで行進した風景は感動的だった。
(裏にはいろいろあるらしいが、、、)
日本では、
その風刺漫画は、遠い出来事で理解が難しい。
日本の何人かの有識者が、
風刺が宗教に関してあまりにも行きすぎると、憎悪を買うだろうと言う。
フランス革命後、
風刺画は国民が権力者を批判する手段であり、表現の自由は守られている。
日本では、皮肉とか風刺とかに対して苦手である。
皮肉を上手に返すことは、下手だし、
風刺漫画もかなり控え目だ。
また、相手への配慮は守るとか。
サザンの桑田佳祐の歌詞に問題があるとか、大騒ぎになり謝罪。
“表現の自由”はどこに。
リッチモンドスクールの英国人講師に聞くと、
シャルリー・エブドは行きすぎではないと言う。
ただ、英国では、
権力者に対してはOKだが、宗教に対しては微妙らしい。
問題は、
このことで、一般のイスラムの人々や、移民の人々が差別を受け、
憎しみの連鎖が起きることが心配だ。
恒例となった、トモ爺さん夫婦のご案内で成田山初詣。
黒龍のお酒が映える酒器
美味な食事に舌鼓、トモ爺さん、ご馳走様
New Year’s Resolution
2015/01/07
新年の抱負 ~ 沢山笑える一年でありますように
生徒さんから頂いた年賀状の中に
“沢山笑える一年でありますように”と言う言葉が目を引いた。
今年は、この年賀状のように、
怒り・不安・悲しみは、笑い飛ばそうと気合を入れた。
資本主義のほころびが見え始め、
ますます広がる格差に心が痛み、
2015年がとても明るい年になるとは思えない。
「今だけ、カネだけ、自分だけ」、という“3だけ主義”が
蔓延っていると云われている。
特に地位の高い立場の人や、為政者、合理的な経済学者に多い。
TVで、したり顔で一説を説いているそのような人々を見ていると、
ムカムカ、イライラ、怒鳴りたくなる。
お正月は、
ケーブルTVで、お気に入りの英国ミステリー*を見続けていたが、
ふっとチャンネルを変えると、
地上波は、どのチャンネルもお笑い芸人の馬鹿笑いばかり。
でもその中で、やはり面白い人の話は楽しい。
彼らには、意識せずに発想の転換ができる才能があるようだ。
今年は毛嫌いせずに、
世の中に流行っているという芸人の話術や発想に大笑いし、
“怒り”を笑いに変えられるよう発想の転換を学ぼう。
*英国ミステリーは
ミス・マープルに始まり、刑事フォイル、バーナビー警部、フロスト警部等、
英国の美しい田園風景をバックに、
英国人独特のユーモアとセンスのある会話で推理を紐解く。
英語の勉強にも最適。