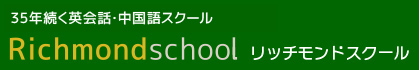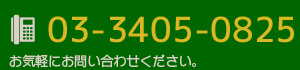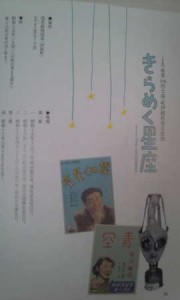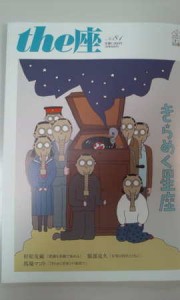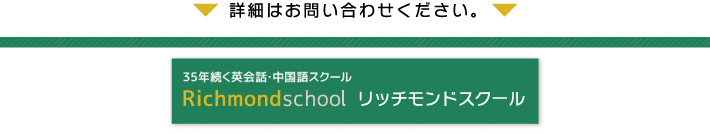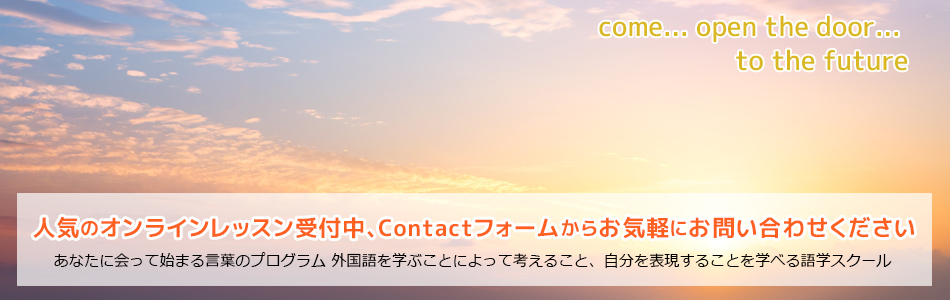
BLOG
お彼岸
2014/09/26
秋分の日はお彼岸のお中日。
暑さ寒さも彼岸までと言うがごとく、このころは気持ちの良い日が続く。
街でも花を持った人々を多く見かける。
お墓参りなのねと、心が和む。
彼岸(あちらの世界)と此岸(こちらの世界)が最も近づくのが、
春分の日と秋分の日だとか。
ご先祖様に会うためにお墓参りに行く風習が出来た。
お盆は、ご先祖様が家までいらして、お彼岸はお墓まで出てこられるらしい。
また、仏教国の中でもお彼岸にお墓参りするのは、日本だけの行事。
御供もののお餅は、春はぼたもち、秋はおはぎと呼ばれ、
春は牡丹の花から、秋は萩の花からが由来らしい。
私も子供の頃からお彼岸のお墓参りは両親に連れて行かれた。
何も考えずお墓参りし、ついでの食事が目当てだった。
今年もお中日に両親のお墓にお参りに行った。
天気も良く、どのお墓にも綺麗な花がたくさん飾られ、華やかな雰囲気だった。
また、一家そろって見えている方が多く、
子供たちの甲高い声がお墓に響き、ほほえましい。
また、お墓参りでは、見知らぬ人でも必ず挨拶し合う。
とても清々しい気持ちになる。
日本には先祖代々、受け継がれた美しい風習がたくさんあり、
次の世代にも受け継いでいってほしい。
山寺
昭和天皇実録
2014/09/19
昭和天皇実録が公表された。
あまりに長い為、新聞やテレビで報道されている解釈を斜めに読み聞いている
だけなので、間違っているかもしれないが・・・・私なりに読み解いた。
激動の時代を生きられた苦悩の日々が実録の中から読み取れる。特に、
第2次大戦に対しては、我々には計り知れない苦しみや思いがおありだったようだ。
昭和天皇は、皇太子時代
欧州を訪問し、第一次大戦の戦跡を訪ねた時、説明を聞きながら
「戦争というのはじつにひどいものだ。可哀そうだね」と涙ぐんでつぶやいたそうだ。
一貫して戦争には反対で、平和的に解決するようにと、言ったにも拘らず、
軍部の暴走で戦争に突入してしまった。
何人かの軍人の名前をあげ・・・は許せないと、密かに側近におもらしになったらしい。
敗戦後、マッカーサーに単身で会いに行き、
「私はどうなっても良いから、国民の衣食住にお力添え頂きたい」と仰った。
「敗戦国の元首は絞首刑にされるため、普通は命乞いをするか、亡命するか、
自分だけが助かる方法を画策するが、日本の天皇は、自分の命を懸けて、
国民を守ることだけを懇願した世界に類を見ない元首だ」と、
この時、彼は天皇に『神のごときの帝王を見た』と感想を述べている。
そのお気持ちが、国民に何とか元気になってもらいたいと、
敗戦直後の全国巡幸に結びついている。
私の個人的な感じでは、御心の内は巡礼だったのではないか?
晩年の懐かしいお姿が甦る。
帽子を掲げて会釈をなさりながら、民衆にお答えになり、
「あ、そう」と仰って、優しくうなずかれるお姿。
今の平成天皇にそのDNAは受け継がれているようだ。
また、状況も戦争前夜にとても似ている。
昨今の不安定な時代にあり、
天皇陛下もことあるごとに平和憲法維持を持ち出され、
ざわついた御心の内をそれとなくお示しになる。
ひっそりと東洋ラン
こまつ座
2014/09/12
今年の1月『太鼓叩いて笛吹いて』を見て以来、こまつ座に惹かれている。
こまつ座は、知られた演出家や舞台関係者や役者さんが、
それとなく観劇している。
知識人や、通の人の好むこまつ座なのだ。
みなが同じ方向を見ているような空間が心地良い。
今回は、『きらめく星座』@紀伊国屋サザンシアター
井上ひさし・作、栗山民也・演出
舞台は浅草のレコード店「オリオン堂」昭和15年ころの戦争前夜。
「オリオン堂」の家族と、下宿している広告文案家や、
そこに集まる人々の庶民の物語。
そこには、井上ひさしが憧れていた暖かい家庭がある。
それぞれみな、時代に翻弄されながらも優しく懸命に生きている。
いつもながら、登場人物一人一人の言葉にずっしりと重みがあり、心に響く。
そんな中でも笑いがふんだんにあり、どこかでホッと一息をつかせてくれる。
井上作品の独特のユーモアのセンス。
この作品の中には、懐かしのメロディーが沢山出てくる。
しかし、軍国主義に向かっていく時代にあって、
歌謡曲は風紀を乱すような音楽として検閲され、
カタカナは敵性語となって使用禁止、
ジャズも敵国の音楽として禁止。
この作品の初演は29年前とのこと。
家族や平和が壊れようとしている現代に、是非沢山の人に観てもらいたい。
ALS筋萎縮性側索硬化症
2014/09/01
今、話題になっている、氷水を頭からかけ寄付をするという
バケツリレーの様な行為。
なぜ氷水かというと、ALSの症状は、身体中がこわばって
氷水を浴びたような状態らしい。
友人のお嬢さんA子ちゃんが、10年くらい前20代の後半に発病した。
私は、ALSの知識はあったが、最も罹りたくない病気だと思っていた。
A子ちゃんも同様、最もなりたくない病気だと思っていたのに、
自分が罹ってしまったと言っていた。
心と身体は全く正常で、全身の筋肉が衰えていき、
徐々に身体が動かなくなって、瞬きもできなくなるなんて。
母親である友人は、彼女にかかりきりで看病している。
看護婦さんを雇ったら、と勧めても、
出来る限りやってあげたいと孤軍奮闘、戦っている。
病気の進行が遅れることを願うばかりだ。
この運動を通して、沢山の寄付が集まり、研究が進み、一日も早く特効薬が
開発されれば、と願う。
ALS以外にも、難病は100数種類以上もある。
なぜ研究が進まないかというと、
一つの理由は、研究しても対象があまりに小規模のため、市場原理で
儲からないから、研究する学者・会社が少ない。
これは、今流行しているエボラ熱も同じことが言えるらしいが、
成人病などに比べて、患者数が余りに少ないと莫大な開発費用をかけても
見合わないとみなされる。
生命も市場原理が優先される。
観光客でごった返していた喧騒がうそのような静謐な夜の浅草
Former enemies unite for World War 1 commemoration
2014/08/25
第1次世界大戦開戦から100年、ベルギーで記念式典
週刊STの記事から;
第1次世界大戦でドイツが中立国ベルギーに侵攻して100年目に当たった日の式典で、
“It opened Pandora’s box,” said German President Joachim Gauck
at the Sain-Smphorien cemetery, who acknowledged that
“it is anything but self-evident to stand and talk to you on this day”
and be warmly welcomed by the nation Germany overran,
Gauck openly spoke of “the great injustice” of invading Belgium and
the civilian brutalities during the first weeks of the war.
(和訳)「パンドラの箱を開けてしまった」とヨアムヒ・ガウク独大統領は
サンシンフォリアン墓地で述べ、ドイツが侵攻した国に温かく迎えられ、
「この日にこうして演説していることは決して自明の理ではない」ことを認めた。
ガウク大統領はベルギー侵略や開戦後数週間続いた民間人に対する残虐行為といった「ひどい不正」について素直に述べた。
こうした歴史を踏まえて、ヨーロッパの国々は平和を目指そうとEUとして一つにまとまった。
一方、69年目の終戦記念日に、 “アジアの国々に多大の損害と苦痛を
与えた”、また”不戦の誓い“という、
歴代首相が繰り返してきた文言を安倍首相は今年も云わない。
ある日の毎日新聞投稿欄に13歳の中学生が、
「平和のために私ができること」という題で、
“平和の世界を築くために自分に出来る事2つ、
一つは戦争や原爆について知ること。
もう一つはみんなと仲良くすること。
一人一人が意識し、みんなが仲良くなり、やがて世界中に広がっていく。“
このような子供たちのためにも平和の世界を目指すのが大人の役目。
資源は有限
2014/08/18
自宅のクーラーを遂に替えた。
約50年近くは使用している。
一度も壊れたことが無いが、最近効きが悪くなったので、
この暑さ、転ばぬ先の杖で、新しく購入した。
別の部屋にあるクーラーも故障気味なのでついでに見てもらった。
13年経つので、部品がないとの事。
たった13年。
車のクーラーも壊れて、今年は遂に全取替えと云われた。
車一台買えるほどの見積だったため直すのは諦めた。
20年近く乗っているが、週一ドライブのため、まだ新車の様だった。
50年使用のクーラーは全く壊れず、その間に別のクーラーは買い替えている。
新しいものは、すぐ壊れるし、直すのと新しくするのと同じ費用。
おかしい。
テレビ、冷蔵庫、クーラー、大型電気商品が短期間のうちに壊れ、
部品も製造中止、仕方なく買い替える。
経済学者は、消費が伸びることで経済のバロメーターを計る。
新製品を次々製造し、資源を無駄遣いし、
自然に返らないゴミの山に埋もれる。
いつか資源は枯渇してしまう。
これで良いの?
資源の争奪戦が戦争の一因でもあるのに。
Photogenicじゃないノラちゃん、本当はもっと可愛いオ顔
戦争と平和
2014/08/11
毎年8月、この季節、特に今年は戦争について考える。
天皇陛下も昨年末のお誕生日で、また今年、新年のお言葉で、
世界平和への願いを何度も仰っていた。
お誕生日のお言葉は、
「戦後、連合国軍の占領下にあった日本は、平和と民主主義を、
守るべき大切なものとして、日本国憲法を作り、様々な改革を行って、
今日の日本を築きました。戦争で荒廃した国土を立て直し、かつ、
改善していくために当時の我が国の人々の払った努力に対し、
深い感謝の気持ちを抱いています。また、
当時の知日派の米国人の協力も忘れてはならないことと思います」
現状の憲法は、押しつけ憲法ではなく、
守るべきものと仰っている。
様々な考えがあり、環境も、世界情勢も日々変化しているから、
恒久平和を日本だけが唱えてもという人も多い。
他国がやっているから、日本も、
やられたらやり返すというような稚拙で幼稚な理論。
松井広島市長の6日の平和宣言、
“憲法の崇高な平和主義のもとで69年間戦争をしなかった事実を
重く受け止める必要がある”
日本の平和主義を、69年も戦争をしなかった強さを世界中に示し、
紛争だらけの世界のお手本になるべきだ。
英語熱
2014/08/04
オリンピック、グローバル化、英語が必須と云われて久しいが、
英語熱は盛り上がっていない。
外国人の接客に困っていても、街中外国人だらけでも、
英語は自分には関係ないと思っている若い人が多い。
貧富の差と同じで、英語が出来る人と、全く出来ない人の差が激しく、
出来ない人は全く興味が無いようだ。
私がリッチモンドスクールを始めた30年ほど前は、
英語を話したいという人で、溢れていた。
50歳以上の年代で、
“英会話”を勉強したことが無いという人は少ないと思う。
みな一度は経験済み。
高いモチベーションで、依然として英語に興味を持ち勉強し続けている人と、
上手になるはずはないと、もう二度とやる気を失っている人と分かれる。
諦めてしまった人に、
もうひと頑張り、努力すれば、何とか楽しめるほどの英語力は付くのに、と
残念でならない。
水泳などと違い、結果が見えづらい為、かなり努力は必要なことは確か。
でも、かじっただけではもったいない。
学校で何年も習ったのだから、成果は必ず出る。
亀の歩みのようで本人に自覚がなくても、確実に進んでいるのだ。
通じる喜び、知るは楽しみなり。
それまで頑張ってほしいと切に願う。
また、拒否反応なしに一度は、試して欲しい。
世界が広がる。
戸田公園花火
暑さの中で
2014/07/29
毎日記録的な暑さが続いている中、
日本中、世界中、不穏な動き。
その上、自分勝手が横行し、疲れが増大する。
電車の中で、
押しのけて座ろうとする若者が多い。
座りたい理由、
ゲームにメールにラインに・・・気持ち悪いほど全員下を向いてスマホの世界。
だから、赤ちゃんマークを付けた妊婦さんが前にいようが、
老人や、身体の不自由な人に気が付かないのか、気が付かないふりか、
自分の世界で、全く、どこ吹く風。
以前、石原元都知事が、電車の中でお化粧する女性に、
条例で禁止させたいと言っていたが、
スマホをしたいのなら、座ってはいけないとか、何とか対策を立ててほしい。
帰って新聞を開くと、
天皇皇后両陛下の被災地に心寄せる追悼の旅の写真。
南三陸町長の言葉に、
「震災直後の4月27日、お見舞いにいらした時、体育館で靴下だけだった私を見て、
皇后陛下はスリッパをお脱ぎになり、
冷たい床の上を歩いて町民を励まし続けた。・・・・」
また今回「両陛下の、震災の風化はさせないという強いご意志を感じた」と。
ご老体にムチ打ち、”雨にも負けず“のように、
東に病気の子供あれば、・・・、南に死にそうな人あれば、・・・、を
実践なさっていらっしゃる。
平和を愛し、気品と気高さと思いやり溢れるお姿、
その無私のお心は、日本中を優しさに包みこむ。
両陛下は、日本人の誇りであり、最後の砦であると思う。
暑くて大変なのは、人間だけではありません。
野良ちゃんも・・
ルーマニア(2)
2014/07/23
先週に引き続き、ルーマニア。
リッチモンドスクールでは、色々な国から先生を採用している。
生徒さんもスタッフも、未知なる世界から沢山の発見をもらえる。
以前ブータンから慶応大学院に留学中だったKingzanが
働いていた時は、生徒さん達とブータン熱に浮かされていた。
Anaがリッチモンドスクールの先生になってからも、
関心事はルーマニア。
彼女は、日本に対して貪欲なまでに興味を示し、
日本を吸収し経験し、楽しんでいる。
日本人として、とても嬉しく、また新鮮だ。
先週は、浴衣と帯を買ってきて、お台場クルーズに行くので、
着せて欲しいと言ってきた。
成人式にも着物を着たし、お茶会、お花見、お能、歌舞伎、
日本を堪能している。
全てに興味を持ち、積極的で、聡明で、明るく、前向きで、勉強家で、
エネルギーが全身に溢れている。
自分自身を信頼・信用している。
日本ではお目にかかれないような若者。
彼女の周りの人々に良い影響を与えている。
彼女曰く、日本の大学は簡単。
ロンドンでは勉強が大変で、いつもチャレンジだと言う。
世界のどこかで活躍し、
いつか彼女の名前が新聞に載る日が来ると楽しみにしている。